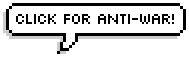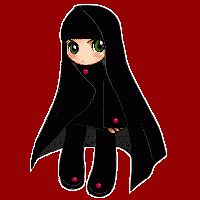大阪のマンガ文化遺産を橋下知事から守れ
・・・行列の消える大阪づくり(@∀@)それが橋下クオリティw
▼大阪府公式ホームページ「知事への提言」のコーナーhttp://www.pref.osaka.jp/j_message/teigen/tijifmt.html
要望、提言、意見をメールで受け付けている。
▼竹内オサム氏の緊急アピール
http://mainichi.jp/kansai/photo/news/20080411oog00m040006000c.html
守れ、子どもたちの感性のために=竹内オサム
◇大阪府の財政再建試案、統廃合の危機高まる文化施設
◇絵本、漫画、紙芝居−−網羅的に継続して収集公開大阪府立国際児童文学館(吹田市)が危機を迎えている。橋下知事の方針で、多くの府有施設が廃止、あるいは他施設に併合されようとしている。国際児童文学館は府立図書館に吸収されるという。改革はいいことだが実施は慎重に。筆者は、漫画、絵本などの調査でよく利用する経験から、当館の存続を強く訴えたい。
館は、早稲田大学の教授であった鳥越信氏の寄贈図書をもとに、84年にオープン。民間の活力のもと財団法人として運営。施設、人件費等を大阪府が負担し今日に至っている。
その後、寄贈資料等を含め、貴重な資料を数多く収集、現在では70万点を数えるまでとなっている。児童文学や絵本に限らず、紙芝居や漫画などを保存している点もユニークだ。
その間、お話し会や展示会、講演会等を開催。府内の地域文庫のお母さんがたや図書館、学校等と連携し、さまざまな読書活動を展開してきた。児童文化に貢献した内外の研究者を表彰する国際グリム賞の運営、世界約50カ国の研究施設や学会との連携、特別研究員制度など、他の公共図書館ではできない取り組みを行ってきた。
こうした地道な活動が可能だったのは、子どもの本や関連資料を、網羅的に継続して収集公開するという、設立時の趣旨が守られてきたから。子どもの読書活動と研究の実績とが、うまくリンクできたためだ。
たとえばキーワード検索もそう。「魔法の出てくる本は?」、こうしたリクエストに答えられるのも、スタッフを中心に、長年データを蓄積してきたためにほかならない。
館の蔵書には、かなりの量の漫画本も含まれる。『週刊少年サンデー』や『週刊少年マガジン』などは創刊号からほぼすべて。『少女』『りぼん』から、戦前の『少年倶楽部』や『幼年倶楽部』などの月刊誌も、大量に所蔵されている。付録類も多い。
紙芝居もそうで、寄贈を受けた4000巻に及ぶ街頭紙芝居は、いまや我が国の大衆文化を伝える貴重な文化遺産とさえなっている。
館のオープンに先立ち、今は亡き手塚治虫氏が記念講演を行った。氏は、赤本漫画時代に活躍した大阪で、漫画も含めて保存する施設ができることを喜んでおられた。その手塚氏の仕事を顧みようとするときにも、館に行けば多くの作品と出会える。
もし府立図書館に統合された場合、まず本がセレクトされ、多数の資料が失われる。真っ先に漫画の類が処分されるにちがいない。
専門のスタッフが培ってきたノウハウも、そのまま継承されないだろう。他の資料も散逸するはず。海外との連携も途切れがちに。寄贈や研究者等の協力も得られまい。
それに、館に行くのを楽しみにしていた子どもたちが落胆する。嘆き悲しむことだろう。
民間ではできないが公共だからこそできる、そんな事業のあることを、知事も府民も再認識してほしい。損得だけで文化は育たない。子どもの感性も豊かにならないはずだ。
館の建物と膨大な蔵書、それに専門のスタッフ。さらには、長年積みあげてきた、子どもの本の普及と研究のノウハウ。それはひとつの有機的な生き物にたとえることができる。
種はひとたび絶滅すると元に戻らない。館も同じだ。その有機的な息の根を一度とめれば、もう再スタートすることは困難だろう。(たけうち・おさむ=同志社大学教授・児童文化)